無事に就職でき、いよいよ破産申立というところまでの経緯をお話します。
家族での引っ越しと、県外への転居
転職先は県外だったため、家族全員で引っ越すことになりました。
子どもが小学校を転校することになり、正直なところ不安は大きかったです。
でも結果的には、「県外に移ったことは良い選択だった」と思っています。
新しい職場での生活と、破産手続きの両立
転職してから1ヶ月後、正式に破産申立を行いました。
破産申立の申請を行うのは、弁護士が変わりにやってくれるので、私はこの日、特段やることはありませんでした。
事前に弁護士から「〇〇月〇〇日に破産申立をします」と聞いていて、申請日当日は「無事に破産申立が完了しました」と連絡を受けたくらいです。
それよりやはり、破産申立までの準備作業が一番しんどかったです…
就職直後ということもあり、仕事を覚えるだけでも大変な時期に、弁護士との電話やメール対応を同時並行で進めるのは、かなりきつかったです。
- 平日の昼休みに電話
- 帰宅後にメールで資料のやりとり
- 必要書類を自宅で印刷・スキャン
など、業務外でも“かなりの負荷”がかかっていました。
さらに、「これはいつの取引?」「なぜこの支払いが残ってる?」など、
自分でも曖昧だった部分を突っ込まれ、思い出すのに苦労しました。
新しい環境への適応もあって、正直「もう戻りたくない…」と何度も思ったのがこの時期ですね…
ちなみに、就職した会社には、最終面接の時に会社を破産させる旨は伝えました。
そのことで、入社時期、入社後に会社破産の手続きや債権者集会のために会社を休むことがあると伝えています。
また、会社の破産、個人の経営者保証ガイドラインの使用についてで、入社後、催促の電話が就職先にかかったりすることは無いとも伝えてましたので、特に懸念点として持たれることはありませんでしたし、むしろ配慮してくれました。
他の転職中に面接を受けた企業には、一次面接の段階では会社をたたむとしか伝えていません。
デリケートな事でもありますので、その段階では事実の一部しか伝える必要は無いと思います。
破産すると「官報」に掲載される現実
会社を破産させると、名前が「官報(かんぽう)」という国の公的な公告に掲載されます。これは誰でも閲覧できるため、知人や地域の人に知られる可能性もゼロではありません。
破産は法律で認められた制度であり、債権者に説明するのは当然のことだと思っています。
でも、全く関係のない人たちの“うわさ”が子どもに向けられるリスクを考えると、県外に移ったことでそれを避けられたのは大きかったです。
経営者保証ガイドラインの準備へ
会社の破産申立が済んだ後は、経営者保証ガイドラインの申請手続きに移ります。
これに必要な書類は、会社の破産申立に比べれば少なめです。
ただし、
- 家計表を毎月しっかりつけること
- 黒字家計であることの証明
が求められるため、「見える化」の作業が日常的に必要になります。
とはいえ、「書類の山」ではなく、「暮らしの見直し」のような感覚に近いものでした。
まとめ:ここが正直、一番つらかった
転職直後の慣れない仕事、家庭の変化、そして破産申立の事務作業。
この時期は、精神的にも肉体的にも、一番しんどい時期だったと思います。
でも、ここを乗り越えたことで、本当の意味で“再スタート”が切れたと感じています。

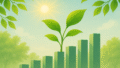
コメント