会社を破産させることが決まり、その後引き継いだ債務は経営者保証ガイドラインを使うことにしました。
ここからは実際にとってきた行動をお話します。
破産申立の半年前:従業員・取引先への説明
まずは従業員にあと3ヶ月で会社をやめることを伝えました。
従業員の給料は有給まで消化してしまって払う予定だったので、会社は破産ではなく辞めると伝えています。
そして、1ヶ月は働いて欲しいが、次の約1ヶ月は有給を消化して欲しい旨を伝えました。
事前に話したことで、混乱を招くことなく従業員全員理解してくれました。
また雇用保険に入っていて会社都合の解雇となるので、有給消化後はすぐに失業給付金が半年受けられました。
それと同時に、仕入先、卸先にもあと2ヶ月で辞めることを伝えました。
もちろん仕入先にも支払いを済ませる予定だったので、大きな混乱はなかったです。
ウチの商品をメインで取り扱ってくれていた会社には同業を紹介したりして、なるべく相手にも迷惑がかからないようにしました。
破産申立の4ヶ月前:残務処理と資産の扱いに注意
従業員は全員いなくなたので、支払処理、売掛金の請求業務やちょっとした残務を行いつつ、備品の整理をしました。
ここで気をつけてもらいたいのは、金額がつきそうな会社の備品は売ったり処分したりしてはいけないということです。
破産後は会社の資産を現金にかえて債権者に分配することになるのですが、事前に勝手に処分してしまうとその処分費が適切だったのか説明しなければなりませんし、売却金の使途は債権者に配られるようになるかチェックされます。
なので、そういったものには手をつけない方が良いです。
破産申立の3ヶ月前:就職活動と資料準備開始
破産申立、経営者保証ガイドラインのための資料を揃えつつ自身の就職活動を行いました。
弁護士に提出した書類一覧(会社分)
・3期分の決算書
・銀行預金残高がわかるもの
・払戻金がある場合の火災保険、自動車保険の証書の写し
・不動産の全部事項証明書
・固定資産税納付書
・債権者や保証人、売掛金未回収の一覧を作成
・会社に残っている備品のリストを作成
弁護士に提出した書類(個人分)
・銀行預金残高がわかるもの
・払戻金がある場合の火災保険、自動車保険の証書の写し
が主なものです。
ちなみに私は昔作った地方の銀行がまだ残っていたので、その残高を証明することに苦労しました。
なので使わない銀行口座はそのままにするのではなくて、できるだけ解約しておいた方がよいです。相続などが発生するときもややこしくなるので。
そしてこの頃から就職活動をはじめました。基本的には転職サイトに登録し、転職エージェントを使いました。この話はまた後日お話します。
破産申立の1ヶ月前:書類完成と弁護士最終チェック
破産申立、経営者保証ガイドラインのための資料が揃い、破産申立用の書類を作成してもらい、弁護士と最終チェックを行います。
このころには私の就職先も決まっていたので、働きながら、休み時間にその書類のチェックを行っていました。
また、弁護士の介入通知をこの頃に送っていたので、借入金の支払い催促は一切ありませんでした。
破産申立:手続き自体は弁護士が主導
実際は弁護士が動いてくれているので、特にやることはありません。
弁護士から「申立しました」と連絡がくるだけでした。また、このころから今度は経営者保証ガイドラインの為の資料の最終チェックに移ります。
会社と違ってやることは、直近1ヶ月の家計簿を作成することです。こ
れは、経営者保証ガイドラインで会社の負債をチャラにしても、保証人が自己破産するような財務状況では債権者も納得しないので、しっかりと黒字家計にする必要があります。
経営者保証ガイドライン申請まで
弁護士が各債権者に説明してくれます。
ただし、書類の最終チェックは他の弁護士に見てもらわないと利益相反になってしまうので、チェックする弁護士にも経営者保証ガイドラインの知識が求められるようです。
他の弁護士にチェックしてもらうといっても、こちら側は何もすることは無く、依頼している弁護士が探してくれます。
このような形で実際は進めていきました。
当然慣れないことも多く、また精神的に負担になることも多々ありましたが、そこはこれから前に進んでいくんだとしっかり考えて、不安の感情と行動を切り離して淡々とすすめていってください。
今後の進め方がわからなかったり不安に思ったら、弁護士に相談すると解決することがよくあります。ここは踏ん張り所なのでがんばってください!

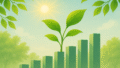
コメント