会社の破産手続きを弁護士に依頼した後、社長にはもうひとつ、大事な選択が待っています。
それは、会社の借金(債務)を連帯保証していた“個人”としてどう対応するかということです。
会社の借金は、社長個人に請求がいく
中小企業では、会社が借りたお金に対して、社長や親族が連帯保証人になっていることがほとんどです。
会社が破産すれば、その借金は保証人である社長個人へと移ります。
この時点で、次の3つのパターンがあります:
自力で返済できる場合 → 任意整理へ
借金の額が少なく、支払いができるのであれば、「任意整理」として分割返済などの対応が可能です。
ただし、現実的には返済できないケースが多いのが実情です。
返済できない場合 → 自己破産 or 経営者保証ガイドライン
借金が大きく返済できない場合は、以下のいずれかを選択することになります:
自己破産
- すべての借入分(会社の借入分や個人のカードローンなど)が免除される(=ゼロになる)
- ただし、99万円を超える現金や資産(車・不動産・株など)は処分される
- クレジットカードが使えなくなり、信用情報に“事故情報”が載る(ブラックリスト)
- 賃貸契約やローンにも制限が出る
- 就ける仕事に制限ができる
経営者保証ガイドライン(会社の借金のみ対象)
- 会社の借入分(連帯保証部分)だけを整理する制度
- 個人の住宅ローンやクレジット借入などは対象外
- 財産制限は基本的に自己破産と同様(ただし5年以上経過した車は残せる場合が多い)
- クレジットカードもそのまま使え、信用情報にも影響しない可能性が高い
- 自宅も残せる可能性がある(金融機関と相談)
どちらを選ぶべきか?
会社の債務が借金のほとんどで、個人のローンが少ない人は「経営者保証ガイドライン」を選んだ方が良いと思います。私はこの経営者保証ガイドラインを使用しました。
この制度には法的な強制力はありませんが、金融庁が後押ししており、多くの金融機関が応じています。
ただし、
📌 自己破産に比べて、この制度を熟知している弁護士はまだ少ないのが現実です。
弁護士費用の目安
- 自己破産・経営者保証ガイドラインともに、弁護士費用はおおよそ60万円〜
- 財産や借金の規模、管財人が必要かどうかで費用は上下します
🗓 依頼のタイミングは「会社破産と同時」がベスト
実際に個人側の手続きを始めるのは、会社の破産申立て後になります。
ですが、同時に弁護士へ相談・契約をしておくと、個人の手続きにスムーズに移行できます。
まとめ
会社の破産で終わりではなく、社長個人としての対応が「次のステップ」として待っています。
“正しく終わらせる”ことで、“正しく始められる”。
私はそう実感しました。

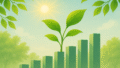
コメント