誰にも言えない、考えたくもない、でも知りたい。
会社をやめる決断、破産、その後の生活のこと。
今、あなたは静かな部屋で、「破産」という文字をキーボードに打ち込むのもためらいながら検索して、どうしようもない不安と戦っているのではないでしょうか?
まさに1年前の私がそうでした。
はじめまして。
私は、従業員十数人の小さな会社を経営していました。
しかし経営悪化と人手不足が重なり、会社を存続させることが難しくなりたたみました。
当時、会社は金融機関から借り入れを行っていて、その連帯保証人は私でした。
そのため、会社を破産させ、個人の借金も整理し、現在は正社員としてサラリーマンとなっています。
このブログは、当時自分が抱えていた不安と、具体的にとってきた方法を書いています。
「会社をたたみたいけど、もしそうなった場合、会社の借金はどうなるんだろう?」
「従業員は?取引先との関係は?そして、自分や家族の生活どうなるんだろう?」
この思いは、会社を経営していた当時からずっと心の片隅にありました。
そんな中で破産について体が重くなるような思いで調べていました。
しかし、検索して出てくるのは弁護士事務所のブログや、売上数億円、負債規模数億円といったそこそこ大きい企業の事例がほとんどでした。
もちろん専門家の情報は必須ですし、大まかに理解することはできました。
でも私の会社の負債は数千万円で、もう少し自分に合った状況の内容が知りたいと思いました。
それと、破産に至るまで、できるだけ周りに迷惑をかけたくないので、金融機関以外の人にはなるべく迷惑がかからないような、そんな「できるだけ静かに、きれいに終わらせる方法」はないか模索していました。
結局、私は弁護士に相談しつつ、取引先、従業員には支払いを完了させ、金融機関からの借金を残して会社を破産しました。そのため、人間関係は破産前後で大きく変わったことはありません。
もしあなたがそのように、できるだけ周りに迷惑をかけず破産をめざし、新たな再出発を模索しているのなら、このブログがお役にたてれば幸いです。
破産は人生の終わりではありません。再出発の一つの選択肢です。
- 破産と倒産の違い
- 会社を破産させるまでに行った準備とその方法
- 社長が会社の借入金の連帯保証人になっている場合
- 連帯保証人になっている社長が次に取る行動
- 破産手続きの内容
- 元社長の就職活動
- 就職後の生活と会社清算までの道のり
- 債権者集会のリアルな体験談
- 再スタートして感じた“生活の変化”──元経営者がサラリーマンに戻って思ったこと
1.破産と倒産の違い
よく混同されがちな、「破産」と「倒産」という言葉から簡単に説明します。
まず「破産」について。
破産とは法律上の手続きの名前です。具体的には借金などの支払いができなくなった人や法人が、裁判所に申し立てて財産を清算し、債務を免除してもらう手続きのことを指します。
そして「倒産」について。
倒産は法律用語ではなく、経済的な状態を表す一般的な言葉です。具体的には会社や事業が資金不足や経営不振で継続できなくなった状態を指します。例えば倒産には次のパターンがあり、破産はその一つとなります。
- 破産(裁判所手続きによる清算)
- 民事再生(再建型手続き)
- 会社更生(大企業向けの再建型手続き)
- 特別清算(会社法上の清算手続き)
- 任意整理(裁判所を通さない債務整理)
私の会社は借入金を返しきれなかったので、破産手続きをとりました。
2.会社を破産させるまでに行った準備とその方法
それでは実際にどのような順番で破産手続きに進んでいったかお話します。
私の場合、
という流れで進めていきました。
1.金融機関に相談(信用金庫)
会社の経営状況が悪くなった時、最初は破産ではなく、任意整理を考えていました。
会社名義の不動産に担保が付いていたので、それを売却して借金と相殺し、残った数百万円の負債はサラリーマンとして働きながら返していこうと考えていました。
そのため、抵当権を持っている信用金庫に相談にいきました。
この信金はウチのメインバンクで、これまでも返済が厳しい時は、元本据え置きで利息のみの支払いに対応してもらったり、割と財務状況を共有しながら密に付き合っていました。
その信用金庫との話し合いの中で、「一番いいように着地できるよう動いてみます」と紹介されたのが政府系の中小企業活性化協議会でした。
中小企業活性化協議会は簡単に言えば、国が認定した公的支援組織で、「収益力改善」や「再生支援」、「再チャレンジ支援」などの財務上の課題について、弁護士などの士業や金融期間と協力しながら支援してくれます。
2.弁護士に相談
その協議会との面談を経て、企業再生に詳しい弁護士を紹介してもらいました。
これまでの人生で弁護士に相談することは全く無かったので、恐る恐る弁護士事務所に行ったことを覚えています。
そして、現在の会社の状況を説明した上でもらったアドバイスは、「任意整理より破産を考えた方がよいのではないか」ということでした。
この時までの私の頭の中では「破産」の比重は大きくありませんでした。
しかし、担保に入っている不動産を売却するにも当然買い手がいないと始まらず、売れなければずっと固定資産税も払っていかなければなりません。
それに、負債と相殺できるほどの金額で売却できる保証もないことから、「破産」をリアルに考えはじめました。
3.従業員、取引先に説明
弁護士との相談から1ヶ月くらい考え、会社を「破産」することにきました。
最初に、従業員にあと3ヶ月で会社をやめることを伝えました。
従業員の給料は有給まで消化してしまって払う予定だったので、会社は破産ではなく辞めると伝えています。
そして、1ヶ月は働いて欲しいが、次の約1ヶ月は有給を消化して欲しい旨を伝えました。
事前に話したことで、混乱を招くことなく従業員全員理解してくれました。
また雇用保険に入っていて会社都合の解雇となるので、有給消化後はすぐに失業給付金が半年受けられました。
それと同時に、仕入先、卸先にもあと2ヶ月で辞めることを伝えました。
もちろん仕入先にも支払いを済ませる予定だったので、大きな混乱はなかったです。
ウチの商品をメインで取り扱ってくれていた会社には同業を紹介したりして、なるべく相手にも迷惑がかからないようにしました。
4.残務処理と破産準備
従業員は全員いなくなたので、支払処理、売掛金の請求業務やちょっとした残務を行いつつ、備品の整理をしました。
ここで気をつけてもらいたいのは、金額がつきそうな会社の備品は売ったり処分したりしてはいけないということです。
破産後は会社の資産を現金にかえて債権者に分配することになるのですが、事前に勝手に処分してしまうとその処分費が適切だったのか説明しなければなりませんし、売却金の使途は債権者に配られるようになるかチェックされます。
なので、そういったものには手をつけない方が良いです。
そして、弁護士との契約、必要書類の準備を行いました。
必要書類を揃えるのは結構大変だったので、詳しい内容は後の弁護士に提出した書類一覧(会社分)に書きます。
5.破産申立
実際は弁護士が動いてくれているので、特にやることはありません。
弁護士から「申立しました」と連絡がくるだけでした。
私の場合、弁護士に相談する前に金融機関に相談していますが、金融機関をはさむのは場合によっては貸し剥がしに合う可能性があるのでおすすめできません。基本的に、信用金庫、地方銀行、都市銀行の順で、企業に寄り添ってくれる度合いが下がります。特に信用金庫は、営利を目的としない非営利の協同組織金融機関という前提があるので、破産や再生案件にも親身になってはくれやすいですが、それでも金融機関より先に、中小企業活性化協議会や弁護士などの専門家に相談した方がよいです。
ところで、弁護士に相談せず、支払い不能状態に陥ってしまったら…
当然ながら会社の買掛金や、従業員の給料、借入金の利息などが支払えなくなると、当然ながら債権者(仕入先・銀行・社員)からの催促が始まります。
この状態になってしまうと精神的にもキツいので、そうなる前に、大変でしょうができるだけ早めに弁護士に相談したほうが良いです。そうすれば破産する際、弁護士が「受任通知(介入通知)」を債権者に送ってくるので、直接の連絡はありません。
3.社長が会社の借入金の連帯保証人になっている場合
会社を破産させても、単純に全ての負債が免除されるわけではありません。
中小企業では、会社の借入に社長が“連帯保証人”として個人保証しているケースがほとんどだと思います。
つまり、会社を破産させても、借金が「社長個人」に回ってきます。
そこで弁護士に、次の3つの選択肢を提示されました。
①個人で全額返済
会社の借入金を、個人で支払います。ただ、(会社の借入金)>(個人の資産)がほとんどだと思うので、このケースが選択できるのは少ないと思います。
②自己破産
所有しているほとんどの財産を手放し、すべての借金を帳消しにする方法です。自己破産の特徴は以下のようなものです。
- 99万円以下の現金と、生活に必要最低限のもの以外は処分される
- クレジットカードは数年間使えなくなり、いわゆる「ブラックリスト」状態になる
- 家を借りる、ローンを組むなどに支障が出る場合がある
③経営者保証ガイドラインを使う(私が選んだ方法)
これは、会社の借金に対して連帯保証した部分だけを整理する制度です。経営者保証ガイドラインの特徴は以下のようなものです。
- 個人で組んでいた住宅ローンなどは対象外
- 99万円以下の現金と、初年度登録から5年を超えた車などは残せることが多い
- クレジットカードの利用や信用情報(いわゆるブラックリスト)にも影響しない場合がほとんど
この方法は「会社の借金だけを清算して、個人として再出発したい」人に向いている方法です。
⚠ 注意点:この制度は“まだまだ浸透していない”
この経営者保証ガイドラインは、法的に強制力のある制度ではありません。
ただ、金融庁が推進しており、ほとんどの金融機関が積極的に応じてくれます。
私も実際、金融機関と相談して進めることができました。
とはいえ、注意点があります。
この制度に詳しい弁護士がまだまだ少ないのが現実です。
「破産は得意でも、経営者保証ガイドラインはやったことがない」という方もいました。
なので、弁護士を選ぶ際には、会社の破産とその負債を被る経営者の今後を考えてくれる人という視点を持つ必要があります。
4.連帯保証人になっている社長が次にとる行動
会社の破産申立をし、その後、連帯保証人はその負債を処理しなければなりません。
個人で会社の負債を任意整理できれば良いですが、実際には難しいと思います。
現実的には自己破産か経営者保証ガイドラインを使用することになると思いますので、そのケースについて見ていきます。
①自己破産
会社の破産申立後、弁護士に依頼することになります。その際、財産状況詳しく提出しなければなりません。
保有可能資産を超えた分は、破産管財人に提出することになります。
また、自己破産でも会社とは別に破産申立しなければなりません。
②経営者保証ガイドライン(私がとった方法)
自己破産と同様に会社の破産申立後、弁護士に依頼することになります。その際、財産状況詳しく提出しなければなりません。保有可能資産を超えた分は、破産管財人に提出することになります。
こちらは破産ではないので、破産申立はありません。
ただし、債権者への説明が必要なので、それは弁護士が行ってくれます。
ここでは、会社の負債以外の個人負債を持っている人はそちらは免除されませんので、債権者にも、その残った負債によって自己破産せずに生活していけることを証明しなければなりません。なので、直近1ヶ月の家計収支の提出があります。
ちなみにですが、自己破産も経営者保証ガイドラインも弁護士に依頼するので数十万円の費用がかかります。
それでも「弁護士に頼む費用もない」という人が取ってしまいがちな道、それが「夜逃げ」です
夜逃げは、決して珍しい話ではありません。
でも、その“末路”は、正直とても厳しいものです。
借金は消えず、社会保障が受けられなくなり、就職も難しくなる…
私が伝えたいのは、「破産しろ」ということではありません。
でも、夜逃げをすると人生を10年以上奪う選択肢だからです。
私は、「破産を選ぶことが、次の人生を選ぶこと」だと気づきました。
あなたも、もし今同じような不安の中にいるのなら、まずは制度を“知る”ところから始めてみてください。
5.破産手続きの内容
破産申立するためには、弁護士に様々な資料を提出する必要があります。
弁護士に提出した書類一覧(会社分)
- 3期分の決算書
- 銀行預金残高がわかるもの
- 払戻金がある場合の火災保険、自動車保険の証書の写し
- 不動産の全部事項証明書
- 固定資産税納付書
- 債権者や保証人、売掛金未回収の一覧を作成
- 会社に残っている備品のリストを作成
弁護士に提出した書類(個人分:経営者保証ガイドラインを使用するために必要な資料)
- 銀行預金残高がわかるもの
- 払戻金がある場合の火災保険、自動車保険の証書の写し
が主なものです。
ちなみに私は昔作った地方の銀行がまだ残っていたので、その残高を証明することに苦労しました。
なので使わない銀行口座はそのままにするのではなくて、できるだけ解約しておいた方がよいです。
相続などが発生するときもややこしくなるので。
会社の破産申立、経営者保証ガイドラインのための資料を揃え、弁護士に破産申立用の書類を作成してもらい、弁護士と最終チェックを行えば破産申立の準備は終わりです。
破産申立自体は弁護士が動いてくれているので、特にやることはありません。
弁護士から「申立しました」と連絡がくるだけでした。
また、このころから今度は経営者保証ガイドラインの為の資料の最終チェックに移ります。
6.元社長の就職活動
会社を破産させれば、もちろん自身の収入も無くなります。
また貯金がたくさんあったとしても、自己破産や経営者保証ガイドラインでは99万円以下の金融資産しか所有できません。
なので、早急に職を探さなくてはなりません。
私は会社があるうちは業務が忙しく、実働は難しかったので転職サイト、転職エージェントに登録しました。
簡単にこの2つを説明すると
転職サイト
- 多数の求人情報が掲載されており、自分で検索して応募するスタイル
- プロフィールを登録しておくと、企業からスカウトが届くこともあります
例:リクナビNEXT、マイナビ転職、doda
転職エージェント
- 自分専任の「エージェント(担当者)」が付き、希望条件に合う求人を探してくれるサービス
- 書類添削、面接対策、スケジュール調整などもサポート
例:ビズリーチ、JACリクルートメント、リクルートエージェント
両方登録して比較した結果
私は転職サイト4社、転職エージェント3社に登録しました。
書類通過率の違い:
- 転職サイト経由:約30%
- 転職エージェント経由:約80%
→ エージェントは企業の求める人物像に合う求人を厳選してくれるため、通過率が高くなる傾向にあると感じました。
利用の費用は
- 求職者は基本無料です(企業側が費用を負担)
- 一部のサポート付きサービスでは、有料オプションがあることもありますが、多くは無料で十分に活用可能です
それぞれのメリット、デメリット
| 項目 | 転職サイト | 転職エージェント |
| 求人数 | 多い(検索可) | 非公開求人が多い |
| 主導権 | 自分 | エージェント |
| 書類通過率 | 低め | 高め(サポートあり) |
| 相性の影響 | なし | エージェントとの相性に左右されることあり |
注意点:エージェントによっては「早く決めさせようとする」こともあるので、自分の希望軸は明確に持っておくと良いです。
ちなみに企業のホームページに求人応募欄がある場合はそこから応募も可能です。
企業としては、転職サイトや転職エージェントから採用すると、一人当たりの採用コストが数十万~数百万かかるので、自社サイトから採用できればコストが下がります。
ただし知名度が低い企業だとそもそも自社サイトだけでは求人が集められなかったり、条件がマッチしていない場合が多かったりと良し悪しのようです。
求職者側も、転職活動に慣れているのであればよいのですが、初めての転職活動で直接応募してしまうと、書類の作り込みや面接対応が甘かったったりで自分の魅力を伝えられないことも多いので、いきなりはおすすめしません。
知人からのオファーは断った理由
ありがたいことに、知り合いの社長や大学の同期から「うちに来ないか?」というお話もいただきました。
ただ、これはあくまで私個人の考えですが──
「人間関係のバランスを壊したくなかった」
彼らとは、これまで良い関係が築けていました。
その信頼関係を、仕事の上下や報酬といった軸に変えてしまいたくなかったのです。
また、もし転職後に「やっぱり辞めたい」と思ったとき、気まずくなってしまうのが目に見えていました。
7.就職後の生活と会社清算までの道のり
家族での引っ越しと、県外への転居
転職先は県外だったため、家族全員で引っ越すことになりました。
子どもが小学校を転校することになり、正直なところ不安は大きかったです。
でも結果的には、「県外に移ったことは良い選択だった」と思っています。
新しい職場での生活と、破産手続きの両立
転職してから1ヶ月後、正式に破産申立を行いました。
破産申立の申請を行うのは、弁護士が変わりにやってくれるので、私はこの日、特段やることはありませんでした。
事前に弁護士から「〇〇月〇〇日に破産申立をします」と聞いていて、申請日当日は「無事に破産申立が完了しました」と連絡を受けたくらいです。
それよりやはり、破産申立までの準備作業が一番しんどかったです…
就職直後ということもあり、仕事を覚えるだけでも大変な時期に、弁護士との電話やメール対応を同時並行で進めるのは、かなりきつかったです。
- 平日の昼休みに電話
- 帰宅後にメールで資料のやりとり
- 必要書類を自宅で印刷・スキャン
など、業務外でも“かなりの負荷”がかかっていました。
さらに、「これはいつの取引?」「なぜこの支払いが残ってる?」など、
自分でも曖昧だった部分を突っ込まれ、思い出すのに苦労しました。
新しい環境への適応もあって、正直「もう戻りたくない…」と何度も思ったのがこの時期ですね…
ちなみに、就職した会社には、最終面接の時に会社を破産させる旨は伝えました。
そのことで、入社時期、入社後に会社破産の手続きや債権者集会のために会社を休むことがあると伝えています。
また、会社の破産、個人の経営者保証ガイドラインの使用についてで、入社後、催促の電話が就職先にかかったりすることは無いとも伝えてましたので、特に懸念点として持たれることはありませんでしたし、むしろ配慮してくれました。
他の転職中に面接を受けた企業には、一次面接の段階では会社をたたむとしか伝えていません。
デリケートな事でもありますので、その段階では事実の一部しか伝える必要は無いと思います。
破産すると「官報」に掲載される現実
会社を破産させると、名前が「官報(かんぽう)」という国の公的な公告に掲載されます。これは誰でも閲覧できるため、知人や地域の人に知られる可能性もゼロではありません。
破産は法律で認められた制度であり、債権者に説明するのは当然のことだと思っています。
でも、全く関係のない人たちの“うわさ”が子どもに向けられるリスクを考えると、県外に移ったことでそれを避けられたのは大きかったです。
経営者保証ガイドラインの準備へ
会社の破産申立が済んだ後は、経営者保証ガイドラインの申請手続きに移ります。
これに必要な書類は、会社の破産申立に比べれば少なめです。
ただし、
- 家計表を毎月しっかりつけること
- 黒字家計であることの証明
が求められるため、「見える化」の作業が日常的に必要になります。
とはいえ、「書類の山」ではなく、「暮らしの見直し」のような感覚に近いものでした。
ここが正直、一番つらかった。
転職直後の慣れない仕事、家庭の変化、そして破産申立の事務作業。
この時期は、精神的にも肉体的にも、一番しんどい時期だったと思います。
でも、ここを乗り越えたことで、本当の意味で“再スタート”が切れたと感じています。
8.債権者集会のリアルな体験談
破産申立を行ってからしばらくすると、担当弁護士から債権者集会の日程候補がいくつか届きました。
債権者集会とは?
債権者集会とは、破産した会社の管轄裁判所が開催し、破産管財人が会社の資産状況や現金化の進捗を債権者に報告する場です。
債権者集会の日程が決定すると、裁判所が破産管財人を選任します。
この破産管財人は、破産者の資産を現金に換え、それを債権者に分配するための中心的な役割を担います。
管財人の役割とやりとり
私の場合、すでに弁護士に会社・個人の資産をすべて報告しており、その内容は管財人に引き継がれました。
また、他に債権者がいないかを確認する目的で、会社宛の郵便物はすべて管財人に転送されるようになります。
基本的に、管財人と直接やりとりする機会は多くありませんが、必要に応じて確認の電話やメールが来る程度です。
私の場合、破産申立から約2ヶ月後に、初回の債権者集会が開かれることになりました。
債権者集会に向けた準備と心構え
弁護士からは次のような説明を受けました:
- 服装はスーツでなくてもOK。ただし、常識の範囲内で清潔感ある格好を
- 債権者が出席しない場合、5分程度で終了することも多い
- 社長(債務者)が発言することは基本的にないが、裁判官から「何か一言ありますか」と聞かれる場合がある。その際には簡単に謝罪の言葉を述べればよい
実際の債権者集会の様子
集会当日、会場は裁判所の法廷でした。
(※ 地域や案件によっては、裁判所内の会議室で行われることもあるようです)
法廷内には、以下の関係者が集まっていました
- 裁判官
- 書記官
- 弁護士(私の代理人)
- 破産管財人
- 債権者(数名)
裁判官から一言求められたため、私は「このたびはご迷惑をおかけし、申し訳ありません」と謝意を述べました。
集会で報告された内容
破産管財人からは、現在の資産状況について次のような報告が行われました:
- 現金化済みの資産や売掛金の回収状況
- 残っている不動産の売却方法(任意売却か競売か)
私のケースでは、不動産の担保を持つ金融機関が任意売却より競売を選択したため、今後は競売手続きに入るとのことでした。
※ちなみに、会社所有の不動産は一旦管財人の管理下に入り、競売時に担保権者に移ります。
集会の今後の流れ
債権者集会は資産の現金化が完了するまで続きます。
そのため、今回の集会では「次回は2ヶ月後に開催」という形で終了しました。
不動産が売却できていれば、その次の集会で終了になる見込みです。
債権者集会は“終わりへの第一歩”
この債権者集会は、破産手続きにおける**“最後の山場”のような存在**です。
実際に参加してみて、手続きが形式的に進むとはいえ、「現実としての区切り」を強く感じる場でもありました。
とても緊張しましたが、弁護士や管財人のサポートのおかげで、落ち着いて乗り越えることができました。
9.再スタートして感じた“生活の変化”──元経営者がサラリーマンに戻って思ったこと
十数年ぶりに、私はサラリーマンとしての生活をスタートさせました。
経営者として働いていた時は、仕事に終わりの時間などありませんでした。
朝早くから夜遅くまで、資金繰りに追われ、休日も頭の中は仕事のことでいっぱい。
でも今は、始業時間に出社し、終業時間に退社するという、決まったリズムで働く日々です。
精神的な負担の軽減
サラリーマンになって、最も大きく感じたのは、心の負担が軽くなったことでした。
- 資金繰りを心配しなくてよくなった
- 毎月の売上や取引先の支払いに追われることがなくなった
- 経営判断の責任を1人で抱え込まなくてよくなった
こうした変化は、自分の想像以上に心を軽くしてくれました。
家族との時間が増えた
また、家族との時間が増えたことも大きな変化のひとつです。
経営していた頃は、土日もどこか仕事モードが抜けず、心ここにあらずな時間を過ごしていたこともありました。
でも今は、週末や祝日には、子どもと出かけたり、家族で食卓を囲んだり──
「家族と過ごす時間のありがたさ」を、あらためて感じています。
40代を過ぎて、「親や子どもと一緒に過ごせる時間は意外と少ない」と言われますが、このタイミングで経営から退いたことは、私にとって“人生を立て直す決断”だったのかもしれません。
とはいえ、感じる“物足りなさ”もある
もちろん、サラリーマンとしての安定と引き換えに、感じる「物足りなさ」もあります。
- 決裁権の限界(提案してもすぐには通らない)
- 業務改善を進めようとしても、変化を嫌がる空気
- 会社の方針について思うことがあっても口を出せない立場
これは、長年「決定する立場」にいたことによる反動なのか、それとも自分の性分なのかは、正直まだ分かりません。
これからの選択肢
今の私は、完全に再び独立するわけではありませんが、サラリーマンとして働きながら、副業や小規模な事業をスタートさせるのが、自分にとって一番自然だと感じています。
経営も、組織の一員として働くことも、どちらも経験してきたからこそ、「自分の強みを活かしつつ、社会ともつながる働き方」を、これからは模索していきたいと思っています。

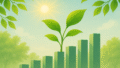
コメント